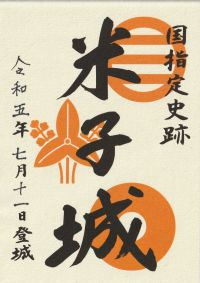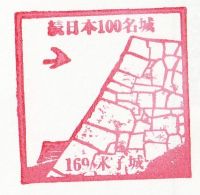| 1467年(応仁元年) |
この頃、山名教之の配下である山名宗之が米子飯山砦を築いたと伝わる。 |
| 1524年(応永四年) |
出雲の尼子経久が伯耆に攻め入り、米子城は尼子氏の支配下となる。 |
| 1562年(永禄五年) |
この頃、毛利氏の尼子氏攻略が本格的になり、米子城も攻撃される。 |
| 1591年(天正十九年) |
吉川広家が米子湊山に築城を開始する。 |
| 1600年(慶長五年) |
関ヶ原の戦い後、吉川広家は岩国へ転封となり、中村一忠が駿河・駿府より17万5千石の領主として、伯耆の領主となる。 |
| 1602年(慶長七年) |
湊山の米子城が完成し、一忠が入城する。 |
| 1609年(慶長十四年) |
中村一忠が20歳で急死し、中村家は断絶となる。 |
| 1610年(慶長十五年) |
加藤貞泰が美濃・黒野より伯耆国会見・汗入郡6万石の領主となり、米子城に入城する。 |
| 1617年(元和三年) |
加藤貞泰が伊予・大洲に転封となり、因幡・伯耆国の領主となった池田光政は鳥取城に入り、米子城には一族の池田由之に3万2千石を与えて配した。 |
| 1632年(寛永九年) |
池田光政は岡山へ転封となり、池田光仲が因幡・伯耆国の領主となる。そして家老の荒尾成利に1万5千石を与えて米子城代に命じた。以後明治まで、米子城は家老の荒尾家代々が城代として預かった。 |